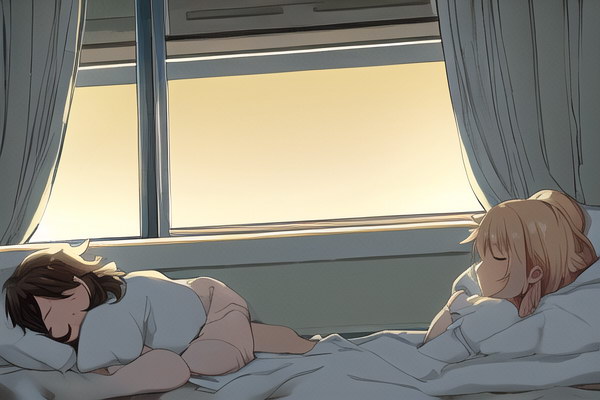もう一歩もう一歩
夢の中で、私は逃げ続けていた。背後には墓場が広がり、砂利道を踏みしめる音が耳に心地悪く響いていた。その先には、見えない恐怖が待ち受けていた。
「止まれ!逃げないと……」
突然、背後から声が響いた。振り返ると、墓石の間から一人の傻子が現れた。その目は狂ったように見え、私を追いかけてくる。慌てて砂利道を走り回るが、彼の足は素早く、いつも一歩先にあった。
「もう……逃げられない……」
恐怖に苛まれて、私は声を上げた。すると、傻子は私の前に立ち止まった。彼の目が私の顔に注がれ、まるで私の心を読んでいるかのようだった。

「なぜ逃げるの君……」
傻子の言葉は、まるで別の世界の言葉のように聞こえた。彼の声は低く、冷たく、心臓に冷たい手を伸ばすように感じられた。
「君が……墓場に来た理由を教えてくれ。」
「……」
私は言葉を失った。なぜか、この傻子に自分の理由を語る気持ちが湧いてきた。そして、彼の目を見つめながら、自分の心の内をさらけ出した。
「墓場に来た理由は……お父さんのことを思い出したからだ。」
「お父さん……」
傻子の声が一瞬静まり返った。そして、彼は微笑んだ。しかし、その微笑みは恐怖を呼び起こすような冷たい微笑みだった。
「お父さんは、君にとって大切な存在だったんだね。」
「……」
私は言葉を失い、ただ傻子の言葉に耳を傾けていた。彼の言葉は、まるで別の世界からの伝言のように聞こえた。
「君が逃げる理由は、お父さんのことを忘れないためだ。」
「……」
その言葉が心に響いた。そして、私はある決意をした。傻子の前で立ち止まり、彼の目を見つめながら、心の内をさらけ出した。
「お父さんのことを忘れないために、私は逃げ続ける。」
「それが君の運命だ。」
傻子は再び微笑んだ。そして、彼は私の背後に立ち去った。墓場の砂利道を走り回る私の背後から、彼の声が響いた。
「君がお父さんのことを思い出したら、もう一度逃げてくれ。」
私は再び砂利道を走り始めた。墓場の恐怖が心の中で消え、その代わりに、お父さんの姿が心に浮かんだ。
夢の中の傻子に追われる恐怖体験は、その後も何度も夢の中で訪れた。しかし、その恐怖は、お父さんのことを忘れないという決意を強める力となった。そして、いつの日か、墓場の恐怖を克服し、お父さんのことを心に刻む日が来ることを願っていた。