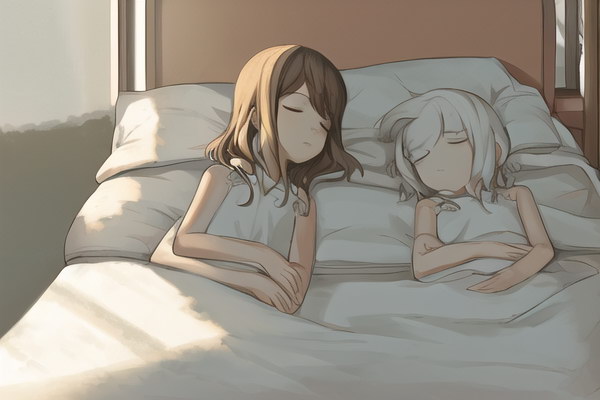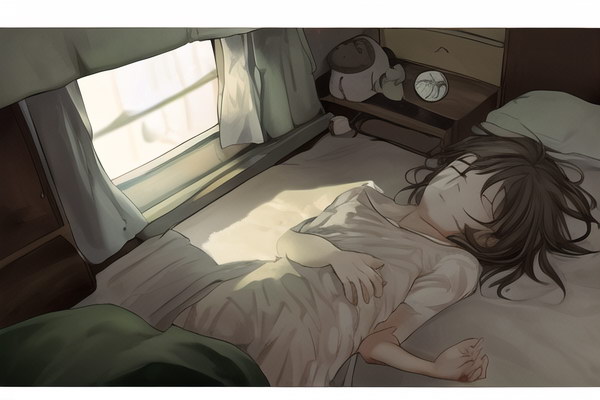打ち鼻で悪夢に包まれた夜の物語
夜の静寂が深まる中、ある青年の心に暗雲が漂い始めた。それは、彼の部屋に隣接する部屋に住む同僚の打ち鼻のせいだった。
彼はいつも、夜の九時を過ぎると眠りにつく。しかし、その夜、異常なことに、彼の頭の中には「打ち鼻」という言葉が何度も浮かび上がり、眠りが深まることはなかった。
「もう、どうせなら夢の中でも打ち鼻が聞こえるように、と願ったんだ」と彼は後日語っている。「しかし、夢の中でも同じ声が響き渡り、恐怖に苛まれた」
夢の中で彼は、ある小さな村に迷い込んだ。村はまるで幽霊の村のように、静かで暗い道が広がっていた。彼は村を出ようと歩いていたが、その先には大きな橋が架かっていた。
橋の上には、彼の同僚が立っていた。彼が近づくと、同僚は大きな声で打ち鼻を始めた。その声が彼の心を襲い、恐怖が高まった。
「おい、あいつ、なんでこんなことをするんだ」彼は同僚に怒りを感じながらも、声をかけた。
しかし、同僚は何も返事をしない。彼はただ、打ち鼻を続けながら、橋の端に向かって歩き始めた。
「あいつ、何を考えているんだ」彼は慌てて同僚に追いかけたが、同僚はその後ろをどんどん遠ざけた。

彼は橋の端に追いつくと、同僚はその先に落ちそうな崖に立っていた。彼は心臓がバクバクと跳ね上がり、恐怖に震えながらも、同僚に声をかけた。
「あいつ、戻ってきて!」と彼は叫んだ。
しかし、同僚は振り返らず、その先に落ちていった。彼は同僚を捕まえようと飛び降りたが、その先に待ち受けていたのは、無限に広がる闇だった。
彼は目を覚ました。彼の周りには、冷たい壁が迫り、彼の心には恐怖が渦巻いていた。
「これは何か夢か」彼は自分の胸を押さえながらも、その恐怖を感じた。
しかし、翌日、彼は同僚にその夢を話した。すると、同僚は驚いた表情を見せながら、自分がその夜、病院に入院していることを明かした。
「実は、その夜、私は風邪をひいて、病院に入院しているんだ。その時、あなたの部屋に近い病室にいたんだ」と同僚は語った。
彼は驚いた。自分の夢と現実が重なったことに、彼は恐怖を感じながらも、同僚に感謝した。
「ありがとう、君。君の声が夢の中で私を守ってくれたんだ」と彼は言った。
そして、その夜、彼は再び眠りについた。しかし、彼の心には、同僚の打ち鼻の声がまだ響いていた。
「また、その声に恐怖を感じる日が来るかもしれない。しかし、今は、彼の声が私を守ってくれることを信じたい」と彼は自分に誓った。