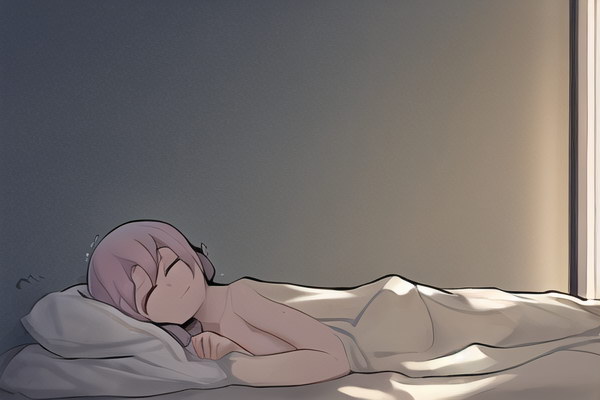夢の中で看病に駆り立てられた妹と老いしの家の物語
夜更けの静かな街並みの中、ある女性の心には波が立っていた。彼女の名前は由紀。その日、彼女の夢の中に現れたのは、幼い頃からの表妹、菜々子だった。菜々子は今も昔も変わらぬ明るさと元気いっぱいで、由紀の心には特別な場所を占めていた。
夢の中で由紀は菜々子と一緒に散歩をしている。しかし、その菜々子の顔には不思議な雰囲気が漂っていた。その後、菜々子が突然息を切らして倒れる。由紀は恐怖と焦りに震えながら菜々子を看病する。しかし、菜々子は何も言わず、ただ無言で目を閉じたまま横たわっていた。
由紀は夢の中で菜々子の看病を続け、彼女の顔に触れると、冷たく、冷たく感じられた。その冷たさが彼女の心を深く刺した。夢の中で時間が流れると、菜々子はようやく息を吹き返した。しかし、その息吹は弱く、不安な予感が由紀の胸を覆った。
その日、由紀は夢の中で菜々子が看病している自分の姿を見て、現実の世界に戻ることにした。その日の夜、由紀はその夢を無意識に覚えていなかったが、翌日、彼女は心の中で菜々子のことを考え続けた。
その日、由紀は自分の故郷、老いしの家に戻ることにした。彼女の故郷はかつて彼女と菜々子が一緒に遊んだ場所であり、彼女の心に特別な意味を持っていた。由紀は自宅に戻ると、菜々子のことを考えながら、家の中を見渡した。
家の中は時間が流れると共に荒廃していった。壁には傷が刻まれ、天井にはカビが生えていた。由紀は心の中で菜々子の姿を思い浮かべながら、部屋から部屋へと歩いていった。
突然、彼女は家の中で菜々子の声を聞いた。その声はとても小さく、由紀の心を激しく揺らせた。彼女はすぐさま声の源を探し、部屋の中を探し回った。そして、家の奥深くにある部屋で菜々子を見つけた。
菜々子はベッドに横たわっており、その顔にはかすかに微笑みが浮かんでいた。しかし、その微笑みには不安が隠されていた。由紀は菜々子に近づき、彼女の手を握った。
「菜々子、大丈夫かい」と由紀は尋ねた。菜々子はうなずき、小さな声で「お兄ちゃん、大丈夫」と答えた。
その言葉が由紀の心を温めた。彼女は菜々子の手をしっかりと握りしめ、彼女の看病を続けた。菜々子は次第に元気を取り戻し、由紀のそばで笑い始めた。
その日、由紀は菜々子と共に老いしの家で過ごした。彼女たちは笑い、話し、過去の思い出を振り返った。そして、夜が更けると、菜々子は由紀のそばで眠りについた。

翌日、由紀は菜々子と一緒に外に出て散歩をした。彼女たちは街並みを歩きながら、笑い合い、話し合った。菜々子は元気いっぱいで、その笑顔に由紀は安心した。
この日々は短く、貴重なものであった。しかし、由紀は菜々子と過ごした日々を心に刻み、彼女の笑顔を忘れなかった。老いしの家と菜々子の物語は、由紀の心に永遠に残り、彼女の人生に新たな光をもたらした。