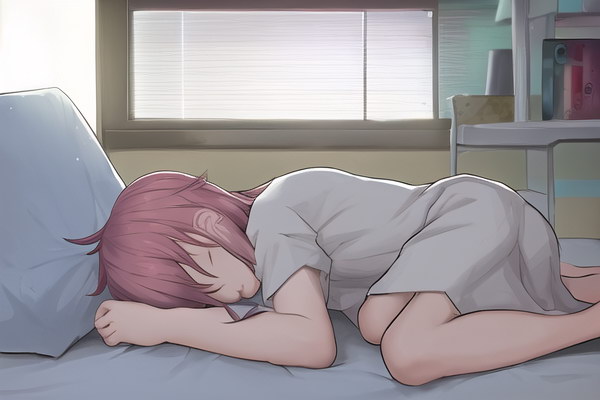夢の中の幼い日々へ時を超えた想い出の旅
夜が深まる中、私は突然の目覚めに驚いた。部屋は静かで、冷たい光が窓辺から差し込んでいた。深呼吸をした後、私は目を覚ましたばかりの緊張感を和らげようと、身を動かした。しかし、その瞬間、何かが異なっていることに気づいた。部屋の空気はまるでかつての自分が夢中で遊んでいた幼い頃の家のようだった。
「ここは」と自問自答しながら、私は目を覚ましたばかりの頭で、この部屋がどこにあるのかを思い出そうと試みた。すると、突然、幼い頃の記憶が蘇った。それは、父親が手作りの木製のおもちゃで作った小さな城、母親が作ってくれた甘いアイスクリームの香り、そして友達と一緒に遊んでいた公園の木々の間から聞こえてきた笑い声だった。
その記憶に包まれながら、私は床を這って進み始めた。部屋の隅に置かれていた古い鏡に向かって立ち、自分の顔を見つめた。しかし、その顔は自分の幼い頃のものだった。長い髪が肩に流れ、大きな目を細く見つめた笑顔が浮かんでいた。
「ここは夢の中の幼い日々だ」と自語りながら、私は部屋を出て、家の中を歩き回った。部屋から部屋へと、かつての自分が過ごした場所を訪れた。父親の工房で作られていた小さな飛行機模型を手に取り、その軽やかな感触に心躍らせた。母親が作ってくれたアイスクリームの箱を見つけ、その香りを嗅ぎながら、幼い頃の甘い思い出に浸った。
そして、友達と一緒に遊んでいた公園へと向かった。木々の間から流れ出る鳥のさえずりが、まるでかつての幼い日々の音を再現していた。公園の砂場で遊んでいた記憶が蘇り、友達と一緒に砂をこね、小さなキャラクターを作るのを思い出した。
しかし、その楽しい時間も一時的だった。突然、現実の声が耳に染み入ってきた。「夢の中の幼い日々はいつか終わる」と言った言葉が、心の中で響いた。そして、その言葉とともに、夢の中の幼い日々が次第に薄れていった。

最後に、私は部屋の隅に戻り、かつての自分が夢中で遊んでいた木製の城に立ち寄った。その城の前で立ち止まって、深く息を吸った。そして、現実世界へと戻るための決意を固めた。
「幼い日々の思い出はいつも心の中にある。それを大切にし、これからも前進していこう」と自誓しながら、私は目を閉じ、目覚めた。部屋は静かで、冷たい光が窓辺から差し込んでいたが、心の中には温かい思い出が満ち溢れていた。