紅樓夢の蟹その大きさとは
「紅樓夢」という作品は、曹雪芹の巨編で、中国文学における古典の一部としてその名を馳せています。その中で、様々な食材が登場しますが、その中でも特筆すべきは蟹です。紅樓夢の蟹の大きさについて詳しく見ていきましょう。
まず、紅樓夢における蟹の大きさについての具体的な記述は多くありません。しかし、作品の中で蟹が登場するシーンを通じて、蟹の大きさについてのヒントを得ることができます。
例えば、第48回では、宝釵が蟹の料理を作る場面があります。この時、宝釵は「蟹は大きさが一尺もあり、その甲羅は深く、肉も厚い」と述べています。一尺(約30cm)という大きさは、現代の一般的な蟹よりもはるかに大きいです。この記述から、紅樓夢における蟹は現代の蟹よりもはるかに大きかったことが推測できます。
また、第58回では、宝玉が蟹の料理を作る際に、蟹の甲羅を「一拳大」と表現しています。一拳大という表現は、現代の蟹でも珍しい大きさを指すと考えられます。この記述からも、紅樓夢における蟹の大きさは現代の蟹を上回っていることがわかります。
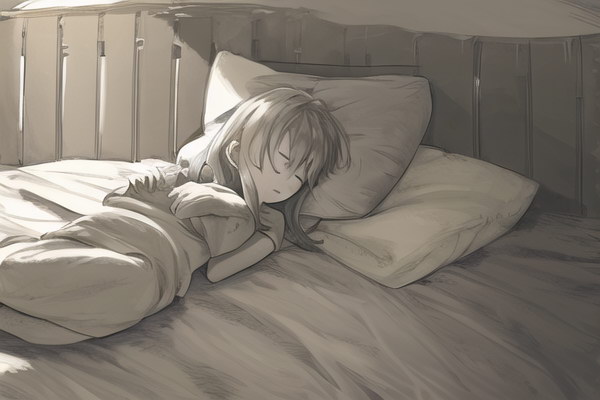
さらに、第70回では、黛玉が蟹の料理を作るときに「蟹は一拳大で、甲羅は深く、肉も豊富」と述べています。黛玉は宝釵よりもさらに蟹の大きさを強調しています。これらの記述を総合すると、紅樓夢における蟹は現代の蟹よりもはるかに大きいことが明らかです。
なぜこのように大きい蟹が登場するのかについては、いくつかの仮説があります。まず、当時の農業技術や養殖技術が現代に比べて未熟であったため、自然に生息する蟹が大きかった可能性があります。また、当時の人々の食生活が現代に比べて豊富であったため、大きな蟹が食べられる機会が多かったとも考えられます。
また、紅樓夢における蟹の大きさは、作品のテーマやメタファーとしての意味合いも持っています。蟹は中国の伝統的な食文化において、繁栄や豊穣を象徴するものであり、その大きさが作品の豊かさや深みを表していると解釈することもできます。
結論として、紅樓夢における蟹の大きさは、現代の蟹を上回る大きさであることがわかりました。この大きな蟹が登場する背景には、当時の農業技術や食生活の豊かさが関係しています。また、蟹の大きさは作品のテーマやメタファーとしての意味合いも持っていることが示されています。









